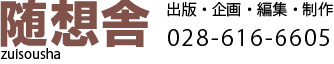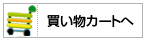【品切】 本商品は現在品切れとなっております。 |
足尾銅山史
村上 安正
著者が古希の歳から稿本として4回に渡って書き継いで完結した原稿を底稿に全面的に書き上げたものである。付章として鉱山用語辞典、各種年表、主要文献、足尾銅山の地質と鉱床など、参考資料を網羅して完稿したものである。古河鉱業在勤当時から鉱山に関する研究を数々発表してきた氏は、特に採鉱技術や労働運動史は世上でも高い評価を得ている。
B5判/上製/656頁/定価8800円(本体8000円+税)
ISBN 4-88748-132-2
著者プロフィール
村上 安正 むらかみ やすまさ
1931年3月 東京・本所に生まれる
1945年3月 東京夜間大空襲で被災、1週間後足尾へ行く
1949年4月 足尾高校を卒業し、古河鉱業株式会社足尾鉱業所に入所
1955年4月 “ぜんこう”に「足尾銅山の想い出」11回連載、以後鉱毒事件から大正8年争議まで計4シリーズ30回の連載をする
1958年7月 編著『足尾銅山労働運動史』(650ページ)上梓、翌年「永岡鶴蔵論」を発表
1973年11月 金属鉱山研究会創設
1986年3月 55歳で停年退職、1年間充電後再就職
1996年9月 ジオテクノ株式会社入社
2005年2月 同社退職
〔主要著作〕
『足尾に生きたひとびと』1990
『銅山の町 足尾を歩く』1999
『鉱業論集』1、2 1986. 3 2000
『足尾銅山史』稿本2001~2004.
〈編著〉『足尾銅山労働運動史』1958
〈共著〉
『技術の社会史』4 1983
『なぜ今足尾か』1983
『金属の文化史』1991
『日本の産業遺産』1986
『日本の産業遺産300選』1993
『利根川 人と技術文化』1999
国立科学博物館『日本の鉱山文化』1996
『黒川金山報告書』1997
文化庁『近代産業遺跡調査報告書』-鉱山-2002.
その他、各地の鉱山調査、論文、報告書、事典の執筆、大学及び鉱山地での講演を実施
目 次
はじめに 1
発刊を祝して
足尾町町長 神山 勝次
東京大学名誉教授 山口梅多頭 6
『足尾銅山史』発刊を慶ぶ
元古河機械金属(株)副社長 高松 剛毅 7
〔近世以前〕
第1章 近世以前の足尾(付 足尾銅山の概要) 25
足尾の位置と現状 25
足尾銅山の位置と産銅量 25
銅山発見以前の足尾 26
勝道上人の来歴 26
中世の足尾 27
第2章 足尾銅山の発見 29
慶長15年以前発見説 29
佐野氏の足尾銅山開発 30
慶長15年の記述 30
群馬県勢多郡東村花輪宿 31
銅山奉行の設置 31
幕府御用の違った側面 32
初期御用銅買い上げの実態 32
第3章 近世足尾銅山の盛衰 35
御用銅山の確立 35
銅山の隆盛 35
銅山街道の開設 35
船輸送と銅山会所 38
灰吹銀の輸送 39
銅山開発の進展 39
足尾銅払い下げ問題 41
五ヶ一銅の輸出開始 42
その後の足尾銅の輸出 44
近世の銅輸出高 44
足尾の産銅量下降とその原因 44
風水害の被害 46
近世鉱山の技術的・経営的限界 47
足尾銅・町売りの許可 48
足字銭の鋳造 49
御手山稼ぎへ 50
嘉永期の泉屋検分 52
第4章 近世足尾銅山の経営と技術 55
近世鉱山の特徴 55
鉱山の探査 55
近世足尾銅山の開発経路 56
採鉱方法の概要 57
間代の基準と実際 57
鉱石の採掘 58
煙毒とヨロケ 58
採鉱夫について 59
採鉱用工具の問題 59
近世足尾銅山の採鉱実態 61
間歩普請について 64
足尾銅山とキリスタン 72
〔明治期〕
第5章 古河経営以前の足尾銅山 77
明治維新後の足尾の動向 77
明治5年の救済策 78
初期明治政府の鉱山政策 79
ゴッドフレイの足尾点検 80
銅山街道の様子 81
銅山の民営 83
第6章 古河の足尾銅山買収 85
古河市兵衛の経歴 85
小野組の鉱山経営 86
岡田と尾去沢鉱山 86
小野組破産と市兵衛 87
草倉銅山の稼行 87
草倉銅山の沿革と古河創業の状況 88
足尾銅山買収の契機 91
足尾銅山の買収 94
銅山引継ぎ 95
足尾銅山仮規則 96
銅山調査と開坑方針の決定 96
第7章 足尾銅山の発展 99
第1節 横間歩大直利捕捉と通洞の開鑿
直利発見までの苦境 99
木村長兵衛の就任 100
鷹之巣直利の発見 101
本口坑取明けと開鑿 102
横間歩の立体的採鉱 104
小瀧坑の開坑 106
大通洞の開鑿開始 107
通洞完工までの過程 110
明治20年代の主要開坑 111
第2節 産銅上昇期の採鉱の現況と賃労働形態の変化
産銅量の急上昇 113
開坑方法の革新 114
切羽請負と飯場の創生 116
飯場制度への移行 118
飯場の種別 120
坑夫飯場の特性 121
雑夫飯場の発展 122
囚人の雇用 123
第3節 経営基盤の強化と技術革新
院内・阿仁両鉱山の払下げ 124
売銅契約とその意義 125
1 前期の技術革新
2つの技術革新 125
道路の改修 126
ドコビールの採用 128
2 第1次技術革新 その一 動力革命
水車から蒸気機関へ 130
洞鋪の水没と処理 131
蒸気機関坑内設置の失敗 131
水力発電へのアプローチ 132
ケスレルの来日と電化の確定 133
間藤発電所の完成 133
間藤発電所の意義 135
地域内発電所の相次ぐ開設 136
3 第1次技術革新 その二 輸送革命
専用鉄道計画の挫折 137
索道の選択 138
馬車鉄道の開設 139
古河橋の完成 140
索道の展開 141
電話の開設 143
第4節 生産過程の改革
1 銅山の生産過程とその変化
鉱山の生産構造とその過程 144
産銅量増大の要因 145
鑿岩機の採用と限界 146
発破用火成品の製造 147
支保作業の専業化 149
人員募集の奇策 150
2 選鉱法の革新
旧来の選鉱法 150
機械選鉱の登場 151
3 製錬法の革新
銅製錬の原理 152
在来の銅製錬 152
直利橋製錬所の新設 153
塩野門之助の登場 153
ピルツ炉の改造 154
水套式溶鉱炉の採用 154
転炉の採用 155
製錬用燃料の変革-コークス使用 158
製錬労働の質的変化 162
第8章 本格的銅山開発とその光と影 165
第1節 通洞竣工と近代的開発への道程
通洞の完成と立坑開鑿 165
鑿岩機の革新 167
採鉱拠点の移動 170
抗内電車軌道による運搬革新 171
採鉱法の変化-階段掘への移行 173
開坑及び階段掘の請負 176
国産ダイナマイトの採用 177
選鉱の拡充 179
製錬過程の難問解決 179
製錬新工場の完成 183
第2節 鉱業都市の形成
近世足尾郷の盛衰 184
銅山発展と人口の急増 185
鉱山専用住居 186
銅山病院の設置 191
銅山小学校 192
商業地の形成 193
商業者の一例 194
広域経済圏との連携 195
第3節 足尾鉱毒問題と足尾銅山の対応
鉱山の鉱毒 197
足尾鉱毒問題の発生 198
鉱毒に対する古河の対応 200
示談契約の成立 201
明治29年の大洪水 201
鉱毒調査会の設置前後 202
鉱業非停止の陳情 203
鉱毒調査会の決定経緯 204
予防工事命令 206
予防工事の資金調達 210
工事設計、資材調達 211
工事資材等の輸送 212
工事人夫の確保と労賃 213
浄水設備工事 214
堆積場工事 216
煙害防止と硫酸製造 217
煙害防止工事 218
予防工事の完成 220
完工祝賀会と水烟係の誕生 221
予防工事以後 221
鉱毒事件の他鉱山への影響 222
第4節 足尾銅山暴動
1 足尾暴動のバックグラウンド
騒擾から暴動へ 222
坑夫の労働環境の変化 223
階段掘の原理と方法 224
坑夫賃金の算定方法 225
役員の構造と待遇 228
精鉱量および間代査定の問題 230
飯場機能の変質 232
鉱毒事件の影響 233
2 労働運動の展開
明治中期の騒動 234
製錬職人の争議 236
永岡鶴蔵の登場 237
草倉から院内へ 238
荒川鉱山での転機 238
院内鉱山でのスト 239
鉱夫税撤廃運動 239
再び院内、そして夕張へ 240
南助松と大日本労働至誠会の結成 240
片山潜の夕張訪問 243
足尾への出発と活動開始 243
労働同志会発足と活動 243
同志会への妨害とその衰微 244
鉱山労働会への再編 245
至誠会足尾支部結成と運動 245
至誠会と頭役、山中委員 246
会社の対応と至誠会 246
至誠会の攻撃と誓願への加速 247
箱の権利奪還 249
飯場割廃止の波紋 249
統一誓願事項の決定 250
3 暴動の経過
2月4日通洞 252
2月5日簀子橋 252
2月5日本山 253
2月6日本山暴動 253
南所長の遭難 253
本山の暴動化 254
至誠会幹部の勾留 255
出兵と鎮圧 256
暴動による損害額 256
4 暴動以後
暴動後の処理 257
坑内操業の再開 258
賃上げ問題の推移 258
検束者家族の救助 259
南助松の妻 259
予審終結から結審まで 260
至誠会幹部の強制退去 261
飯場制度の改変 262
鉱山・炭坑の争議・暴動 262
暴動直後の文学 263
〔大正期〕
第9章 変動する銅市場と河鹿の発見・開発 267
第1節 河鹿開発と大量処理体制への道程
変動する世界銅市場 267
国内銅鉱業の推移 268
足尾の産銅推移 269
河鹿の出現 270
天狗河鹿から300尺河鹿へ 271
救世主としての河鹿 273
河鹿開発の技術的基盤と改善 273
採鉱の労働形態と人的構成の変化 275
第2節 生産過程の変革
1 採鉱技術
探鉱の成果 279
採鉱法 281
機械掘の進捗 282
採鉱機械化の過程 284
足尾式鑿岩機の生産開始 284
大型圧気機の設置 287
鑿焼の機械化 287
爆薬製造の民間開放 287
液体酸素爆薬の試験 288
採鉱の坑内基準点及び鉱況報告 288
排水系統の一元化 291
送風機の設置 291
坑内運搬の改革 292
支保技術 294
カーバイト工場の稼動 295
2 選鉱技術
在来の選鉱過程 296
浮遊選鉱法の採用 296
選鉱の処理系統と増強 298
廃滓と廃水の処理 299
3 製錬技術
製錬操業の概況 301
大正末の製錬実態 301
製錬の附属設備 302
鉱煙処理問題 304
気流観測による調節 306
コットレル集塵装置と金属鉱業研究所 307
電気集塵機の実用試験 308
集塵の経過と対策 309
試験集塵機による研究 310
副製品工場の稼動 311
第3節 社会環境整備の道程
1 足尾鉄道の完成
足尾鉄道の開通 312
鉄道開設までの経緯 313
鉄道工事の開始と竣工 315
鉄道開設による環境整備 316
2 教育機関の整備拡充
銅山小学校の現況 317
各種補習学校 318
坑夫養成寮 318
工手教習所の開設 319
私立足尾銅山実業学校 320
3 居住環境の整備
鉱夫居住の概況 320
上水道の状況 323
倉庫制度の推移 326
三養会の創設 327
銅山病院の拡充 328
汚物処理 329
共済制度 329
娯楽設備・年中行事 330
弔事葬祭 331
第4節 労務事情の変革過程
1 労働力調達の変化
労働力調達の実態 332
鉱夫募集への援助 333
雇入れ前の職業 335
雇入れ条件 335
解雇の種類と内容 335
脱走の要因 336
長期勤続の奨励 337
模範鉱夫選賞 339
永年勤続者の実例 339
2 労働力調達圏の変化
寄留の実態 340
鉱夫原籍調べ 340
頭役の原籍 341
第5節 飯場制度の変遷過程
制度変遷の理念 342
頭役使用細則の制定 342
第一次飯場制度改革の意義 344
大正2年の改革 344
その後の改革 345
共同炊事場の開始 345
飯場組合の沿革と機能 346
飯場間の金融機関 347
鉱夫飯場組合の一部改正 348
頭役辞職勧告から撤廃覚書へ 348
飯場制度の改善 349
飯場制度の改革 350
居住区域世話役への移行 352
飯場の趨勢と変質 353
第6節 労働運動の高揚と挫折
1 大正8年の争議
友愛会足尾支部の結成 353
松葉鏗寿の来歴 354
同盟会の胎動 354
会員獲得運動 356
人事課の創設 357
同盟会の結成 358
要求提出とストライキ 359
鉱業所の回答 361
全国坑夫組合足尾支部の結成 361
桝本卯平反対運動 361
鉱夫飯場組合と同盟会 362
300名の人員整理発表 363
飯場制度撤廃で結集 364
頭役辞職勧告と金田座大会 364
鉱業所と交渉開始 365
11月27日の騒擾 367
幹部検挙と同盟会の反発 369
幹部拘引と本店交渉 370
所長交代と操業開始宣言 371
調停工作と同盟会の硬化 372
レッド隊と警察の調停 373
争議の終結 373
騒擾事件の結審と後日談 374
2 古河商事破綻と古河の経営危機
古河商事の発足 375
大連事件の発生と収拾 376
古河商事の破綻 376
足尾鉱業所の合理化 376
足尾鉱業所事務所の売却 377
3 鉱夫総連合会の結成と労働争議
同盟会の弱体化 379
製錬の争議 379
鉱夫総連合会の結成 380
大正10年争議の開始 380
麻生來山と要求提出 381
スト突入と大量解雇通告 381
馘首反対デモ 383
馘首者家族大会 383
ストの拡大 384
坑夫罷業の半面 384
女房の上京陳情と波紋 385
争議打開策の模索 385
争議の解決 386
足尾争議の波紋 387
足尾のメーデー 388
箱元帳簿公開訴訟 388
4 製錬争議からヨロケ対策まで
労働形態の劇的変貌 388
鉱業所首脳の交代 389
婦人問題講演会 390
ダイナマイト事件 390
大正13年争議 391
ヨロケ対策決議まで 392
「ヨロケ」パンフの刊行 392
社会局の「ヨロケ調査」 393
5 無産政党運動
統一政党結成の苦渋 394
足尾公民党の結成と成果 394
日本労農党の中核として 395
足尾連合会の解散 395
第7節 労資懇談制と鉱職夫組合
飯場鉱夫組合の改革 396
採鉱夫組合の組織と問題 396
採鉱夫組合規約の概要 397
採鉱夫組合連合会規約の概要 397
鉱職夫組合総連合会の規約 397
採鉱夫組合の事業 398
評議員会の提案事項 398
反労働組合団体の創立 398
小瀧共愛鉱友会の趣意と規則 399
交誠会規約 400
会社主導団体の異同 400
第8節 大正期のその他の事件等
鉱山都市の爛熟 400
原敬暗殺事件 401
社内報『鉱夫之友』 402
『鉱夫之友』の内容 403
足尾を題材とした文学 404
〔昭和前期〕
第10章 昭和恐慌期の足尾銅山 407
第1節 昭和前期の概況
昭和期の時代区分 407
恐慌期の日本産銅業と古河 407
足尾銅山の概況 408
第2節 採鉱の実態
探鉱の成果 410
採鉱の方法 411
進み掘の展開 414
シュリンケージ法 414
鑿岩機使用の採鉱実態 415
総合間代の意義 418
第3節 選鉱・製錬の実態
選鉱能力の増強 419
製錬の概況 420
硫酸製造試験 420
酸化ニッケル製造 421
第4節 要員調達と労務対策
坑内の労働環境 421
職種別の労働管理裁定と賃金原則 422
半本番制の採用 422
平均賃金の推移 425
人員調達の状況 425
第5節 福利厚生その他
安全委員会 426
付属病院の状況 427
健康保険組合 427
銅山体育会の発足 428
全山運動会 428
音楽協会 429
盆踊り大会 429
金融部の設置 430
足尾の歌謡 430
足尾俳壇の隆盛 431
鉱業報国会の発足 432
〔昭和中期〕
第11章 戦時体制下の足尾銅山 435
第1節 戦時下主要銅山の一般的状況
戦時生産政策の概要 435
太平洋戦争開始と非常時増産命令 435
主要銅山の産銅推移 436
戦時下鉱山の分析視点 436
戦時下足尾銅山の採鉱条件 437
安定生産体制の立案 437
第2節 朝鮮人および中国人の連行問題
朝鮮人等の連行の背景 438
朝鮮人連行の経過 438
職種別配置構成 439
賃金の実態 440
稼働率 441
労働に対する認識と評価 441
個別の労働環境 442
住環境の状態 442
労働災害 443
逃亡の分析 444
中国人強制連行 445
就労部署と居住管理 446
坑内労働の実状 447
外人俘虜 449
徴用と学徒動員 449
第3節 日本敗戦と戦後処理
敗戦直前の状況 449
戦後の混乱 450
中国人問題 451
朝鮮人問題の展開 452
大川副所長の登場 454
在日朝鮮人連盟との団体交渉 455
朝鮮人問題の解決 457
第12章 戦後の足尾銅山 461
第1節 戦後への胎動
敗戦後の古河鉱業 461
古河従純の退任 461
古河庭園に至る経緯 462
どん底の足尾銅山 462
足尾銅山労働運動の再生 463
要求書の提出 467
鉱業所の回答 468
地区内労組の結成 469
県内組織化の主導 469
危機突破県民大会 470
鉱山復興とヨロケ撲滅宣言 470
第2節 鉱山復興の取組み
鉱山復興のネック 470
補給金支給までの過程 471
NRSの鉱山調査 471
探鉱の模索 472
食糧危機突破の取組み 472
危機突破県民大会 473
町民運動への展開 473
農民への感謝活動 473
5.31食糧スト 473
食糧獲得人民大会 474
床芋とジャガイモ騒動 474
再び町民大会 474
人員の不均衡対策 475
坑内応援と炭坑応援 476
女工の過程復帰と鉱員の停年制実施 476
ノウハウを活かした自家製造 476
天然痘の発生 477
キャサリン台風の猛威 477
キティ台風の被害 478
世話役制度から総代役へ 479
第3節 補給金撤廃から合理化実施まで
価格差補給金の経緯 481
経済九原則の実施 481
補給金撤廃の影響 482
生産業復興運動の曙光 482
重液選鉱法の実用化 482
朝鮮戦争と銅価 483
足尾銅山再建整備案の提示 484
具体的再建整備案の発表 487
労組との質疑 490
労組の再建整備対策 491
経協再開から団体交渉へ 492
労組の最終的態度決定 493
人員整理の協定書要約 493
人員整理の処理 494
古河・足尾王国の解体と脱皮 495
〔昭和後期〕
第13章 高度経済成長下の足尾銅山 499
第1節 高度経済成長と足尾銅山
戦後停滞からの脱却 499
古河鉱業の業績推移 500
足尾の産銅推移 500
第2節 戦後日本鉱業の技術革新
戦後鉱業技術の展望 502
探査技術 502
採鉱技術 503
選鉱技術 507
製錬技術 508
第3節 戦後復興期の足尾銅山(採鉱・選鉱)
合理化後の足尾銅山(下部開発) 508
上部再開発の進展 509
坑外鉱の探査と開発 510
万年坑井開鑿 511
広域地質調査 511
試錐探鉱の拡大 512
使用鑿岩機の変革 512
採鉱法 513
採鉱成績 514
運搬の合理化 514
支保技術 515
坑内排水ポンプの自動化 516
キャップランプの採用 516
選鉱技術 516
第4節 自熔製錬法の操業開始
新製錬法への模索 517
百渓氏の仲介と訪芬 517
自熔製錬の具体化 518
硫酸製造への道程 518
自熔製錬の竣工 519
製錬所独立とその後 519
海外鉱石の確保 520
千葉製錬所の挫折と共同製錬所への参加 521
自熔製錬法の国内席巻 521
第5節 合理化の推進
昭和25年合理化以後 521
鉱職分離の前段 522
社連の分離強行 523
28年の合理化 523
29年合理化の前哨 523
小滝の撤収と人員整理 524
小滝移転 525
坑口番割の開始 526
源五郎沢堆積場の決壊と応急対策 526
簀子橋ダムの着工と完成 526
下部開発に伴う運搬合理化起業 528
組夫の坑内採鉱開始 528
第6節 労務関係と春闘の推移
実地見習員・事務員制度問題 529
指導鉱員制度の発足 530
模範鉱員制度の廃止 530
賃金闘争の激化 530
人身売買と金ヘン泥棒等 530
27年春季波状ストとピケット 531
火炎ビン事件 532
労組主婦の会結成 532
28年アルバイト闘争 533
苦悩の29年闘争 533
小滝撤収頃の社宅事情 533
厚生施設改善要求 534
労組幹部不信任成立 535
30年全鉱春闘 535
第7節 坑内請負体制の変化と保安問題
鑿岩夫の基準外問題 536
秋田からの高卒採用 536
生産部の設置 536
敗戦直後の賃金体系 536
賃金配分の変化 537
坑内夫能率給の推移 537
請負鑑定基準 538
鑿岩夫の鑑定基準 539
方台数0.5以下の廃止 539
運搬夫の鑑定基準 540
運搬夫の認定作業 540
支柱夫等の能率給 540
坑内喫飯所の新設 540
労働保護法制の歩み 541
鉱山保安法の内容 541
保安法施行前の状況 542
昭和期の災害推移 542
戦後の状態 543
第8節 職業病対策の推進と珪肺法成立
ヨロケ撲滅運動のメッカ 543
昭和戦前期の足尾ヨロケ対策 544
珪肺撲滅運動の再開 545
戦後の検診結果 545
珪肺協定までの道程 546
珪肺問題の世論形成 546
珪肺法成立へ 547
珪肺法からじん肺法へ 548
第9節 鉱山労働者の労働・生活意識の変化と文化活動
鉱山社会の特殊性と普遍性 548
足尾の近代社会と労働者 549
坑夫気質の変遷 549
進鑿気質の変遷 550
支柱気質 551
車夫気質 551
技能修得方法の歴史的変遷 551
見習の養成と試験 552
職人気質の崩壊と変化 553
生活意識の変化 554
戦後の文化活動 554
文化会館の建設と野州路 555
映研の発足と活動 555
短詩型結社の活動等 555
組合文化賞の創設 555
足尾銅山労働運動史の発刊 556
フォークダンスと「うたごえ」運動 556
第14章 閉山への道程 557
第1節 産業構造の変貌と銅鉱山
貿易自由化と合理化の展開 557
一次産業の凋落 557
銅鉱業の光と影 557
古河の金属鉱山閉山 558
第2節 合理化の進展
合理化の質的変化 559
三養会の分離独立 559
鉱業政策確立運動へ 560
銅自由化対処の合理化方策提案 561
鉱業審議会の中間答申まで 562
危機突破大会の成果 563
病院と現業の合理化 563
40年の合理化提案 563
山元整員問題の修正決着 565
自立体制確立提案(昭和41年) 567
確認事項の内容 568
管理機構の統廃合 569
付属病院の改築 569
銅山特設電話の自動化 570
駒屋所長の登場 570
自立体制確立提案 570
中央交渉の妥結 571
高松所長の登場と新操業体制 571
沈澱銅の採取増強 572
クルー作業の拡大 574
坑廃止と採鉱係制へ 574
社内機械工場への配転 574
陶管製造の準備 574
第3節 閉山への過程
足尾事業所の発足 574
大幅赤字と善後策 575
マスコミの閉山報道 576
労組の対応 576
地方自治体の対応 577
閉山対策町民大会 578
閉山を正式提案 579
金属鉱業危機突破全国大会 579
労組回答の会社検討内容 579
本格的交渉の開始 581
条件闘争への転換 581
退職条件回答 582
ストライキ突入 582
閉山条件の解決 582
2月24日閉山式 583
就職斡旋の経過 583
斡旋委員会の活動 584
じん肺管理区分者の再就職 584
閉山退職手当等の総額 585
付属病院問題 585
三養会の縮小 585
閉山を詠った俳句と短歌 586
第4節 閉山後
(株)古河の誕生とその後 587
日足トンネルの開通 587
国鉄民営化と足尾線 588
過疎の進行 588
鉱害問題の再燃と解決 589
昭和の文学等 590
補 章 591
明治10年頃の足尾歴史地図 593
足尾銅山鉱床図 594
鉱山用語抄 595
足尾銅山史年表 621
足尾銅山ハイテク年表 627
足尾銅山産銅表 628
主要文献 629
足尾銅山の地質と鉱床 635