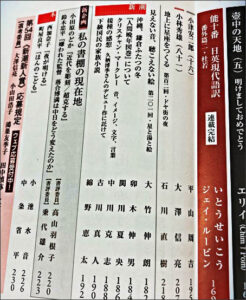旅は詩(うた)だ。
「新潮」編集部から、突然随筆の原稿依頼がメールで舞い込んできたのは、三泊四日の沖縄出張の帰路、那覇空港羽田行搭乗ゲート前の出来事だった。栃木県宇都宮市で「随想舎」という地方出版社を生業としている者とはいえ、文芸誌などにはとことん無縁なボク。読書といってもノンフィクションばかり読んでいるので、文芸にはほとんど縁がないのだ。そんなボクになぜ?とは思ったものの、「テーマ」はなんでもよいとのこと。飛行機の中で雲を見下ろしながら、沖縄を代表する詩人山之口貘と鎌倉文士のひとりで詩人である田村隆一を縦軸に地方出版のあり方を書くことにした。その表題が今回の「沖縄、鎌倉ふたつの冬」である。
沖縄は今回が四回目。その内一度は石垣島と西表島だから沖縄本島は三度目ということになる。しかし、その三度とも観光ではないので、国際通りから脇道を入った幾筋もの路地や喧噪がみなぎる牧志公設市場周辺に点在する「せんべろ街」のほかは、第二次世界大戦下、国内唯一地上戦となった沖縄戦の戦没者を慰霊する「摩文仁の丘」と、新基地反対運動で訪れた辺野古現地、かつて旧日本陸軍の野戦病院だった真っ暗なガマに入ったことくらいしか知らないのだ。
しかしそんな中で、テレビロケで訪れた沖縄本島北部に位置する大宜味村立芭蕉布会館に向かう坂道の先に建てられていた山之口貘の詩碑だけは記憶に残っている。詩碑には「芭蕉布」と題された一節が刻まれ、「母の言葉を おもい出したりして 沖縄のにおいを なつかしんだものだ」とあった。きっと芭蕉布に沖縄、そして母の温もりを感じていたのだろう。彼は1903(明治36)年、那覇に生まれ、22年上京。一度帰郷するも詩稿を携え再び上京し、佐藤春夫や草野心平らと知遇を得て「歴程」の同人となった。そして本土の詩人には真似のできないような詩作を続けた。それは沖縄人ならではの感性の賜であろう。
ボクとそんな山之口貘との出会いは、お恥ずかしいことに彼の詩集ではなく、いまは亡きフォークシンガー高田渡の楽曲からだった。知る人ぞ知る高田だが、彼は音楽活動を始めた途中から自ら詞を書くことをやめ多くの現代詩をもとに楽曲をつくり歌った。赤貧まみれの生活のなか放浪を続けた山之口の詩には、特に惚れ込み、彼の代表曲である「生活の柄」をはじめ「貘さん」の詩だけを編んだアルバムを発表している。また、没後出版された最後の詩集「鮪に鰯」の一編も高田によって歌い継がれた。
そんな中、偶然に出会ったのが前述した詩碑である。芭蕉布会館の方と詩碑の前で話をすると、「もっと全国で知ってもらいたい詩人ですね」と言葉少なに語ってくれた。その時も今回と同じ冬の出来事だった。海はどこまでも青く広がり小さな白波が立っていた。しかし、南国とはいえど海風は冷たく、その後、那覇に戻って呑み屋街をふらつき沖縄料理を肴に痛飲していると店の人は、「寒い、寒い」という言葉を繰り返していた。宇都宮から来たボクには、那覇は暑すぎて上着を脱ぎ、腕まくりをしているほど。本土とは約十度は違う気温を自分の肌で体感させられた場面だった。
舞台は変わって鎌倉。沖縄から帰った週末、ボクは電車で鎌倉へ向かった。鎌倉へは週末を利用して、月に一度は酒を呑みに行く。鎌倉といっても小町通りなどの喧噪から離れた材木座や腰越漁港である。田村隆一は、山之口が本土に渡った翌年、東京で生まれた。鮎川信夫らと「荒地」を創刊し戦後の詩壇を牽引した。『ぼくの鎌倉散歩』というアンソロジーには、鎌倉を舞台にした詩やエッセイがまとめられていて面白い。この十二月初頭は、紅葉が真っ盛りで、沖縄のピンクの花の街路樹「トックリキワタ」とはまるで趣がちがう。訪れた二階堂の奥にある覚園寺の紅葉に覆われた境内は見事だった。同じ日本でも北と南ではこうも違うのかと、その日本列島の広さを改めて実感したしだいである。
田村は、1970(昭和45)年に東京から材木座に住まいを移し、稲村ヶ崎や二階堂と転居を繰り返し文字通り「鎌倉の人」となった。そしてエッセイの中で、朝からビールを呑み、谷戸を散歩し、路地を巡り、夜な夜な得体の知れない人士が集まる「養老院的居酒屋」で夜更かしを楽しんだと書いている。そして、生涯五回結婚し、四回目の結婚を機に鎌倉の人となったのだからうらやましい限りだ。
田村の残した詩の中で、「言葉などおぼえるんじゃなかった」という一節がある。ボクが沖縄と鎌倉を比べて思うのは、沖縄では言葉のやりとりは日常的以上に必要で、鎌倉では言葉はあまり必要ではなかろうかということだ。多弁な南国とは異なり、鎌倉では言葉は最低限あればいいと思う。それは、商店街と散歩道との違いでもあると言い切れる。ボクにとっての鎌倉は散歩道であって、町外れの観光客がこない地元民御用達の蕎麦屋や地魚の居酒屋で昼酒を呑む多幸感がそう思わせてくれるのだろう。山之口貘と田村隆一の詩も、その生活も時代背景もまったく別の世界であるが、その環境の違いをつらつらと考えさせてくれた一週間だった。
栃木県内に埋もれたさまざまなモチーフを掘り起こし、地方出版社をはじめてはや三十七年。陰の薄い県には、田中正造をはじめ、日光、足尾などたくさんの宝物が眠っている。そして、その動機は、憧れていた出版社に入社できるほどの能力がないことは明らか、ならば自分で事務所を興してしまった方が手っ取り早いという結論からだった。それに子持ちで大学を卒業し、職安の紹介で就職した印刷会社で得たノウハウもその気持ちに拍車をかけた。無謀さと無計画性、そして楽観性だけが今日までを支えてきたと考える今だ。
山之口貘の放浪性と田村隆一の奔放性は、どちらも精神が解き放たれているということに尽きる。また、ボクの放浪性と奔放性は地方出版社という世間ずれした生業であるからこそ成しえたことだ。あといつまで「放浪」と「奔放」の毎日を続けられるか分からないが、このふたつがあってこその地方出版社だと思わずにはいられない。
「文芸新潮」(新潮社)2022年2月号掲載