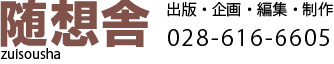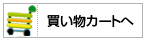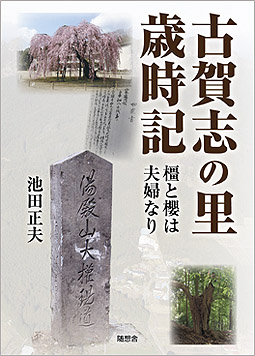
古賀志の里歳時記
橿と櫻は夫婦なり
池田 正夫
聖なる地・古賀志の信仰と歴史を網羅。古賀志山のもう一つの魅力がここにある。
宇都宮市の西北に位置する古賀志山は、標高583メートルの低山ながら、切り立った峰々はひときわ異彩を放っている。あたりには岩山が多く、ハイキングはもとより岩登りのゲレンデとしても知られ、さらに近年はパラグライダーも盛んで、これらアウトドア趣味の人々で賑わっている。
しかし、古賀志山の魅力はそれに尽きない。古くから開けた山里には豊かな生活の歴史があり、聖なる山を崇める様々な信仰が息づいてきた。樹齢数百年を誇る樹木は神木となり、山裾に点在する洞窟や滝は神仏のよりつく聖地とされ、多くの神社や石仏が祀られ、今なお受け継がれた祭りが繰り広げられている。
本書は、そうした古賀志の里の信仰と歴史を、当地出身の著者が古文書をひもとき丹念な調査に基づいてまとめたものである。それはまさしく、「ふるさとの歳時記」にほかならない。
A5判/上製/392頁/定価3080円(本体2800円+税)
ISBN 978-4-88748-257-9
2012年3月30日 第1刷発行
著者プロフィール
池田 正夫 いけだ まさお
昭和13年3月5日 栃木県宇都宮市古賀志町生まれ。
鹿沼高卒、宇都宮大学学芸学部卒。専門は数学および技術科。宇都宮市立姿川第一小学校長(平成5年~7年)、宇都宮市立泉が丘小学校長(平成8年~9年)を歴任。
退職後、宇都宮市立中央公民館社会教育指導員(平成10年~13年)を勤めた。退職後に山行を始め、平成11年から丸6年掛けて日光修験三峯五禅頂の全行程を6巡。
《著書》
『全踏査 日光修験三峯五禅頂の道』(随想舎)
目 次
発刊に寄せて 柏村祐司
はじめに
愛郷歌 古賀志めぐり
1 古賀志山
2 瀧大権現
(一)瀧大権現神事祭礼
(二)瀧大権現の拝所
3 大日窟
(一)大日窟の再興
(二)出羽三山湯殿山の勧請
(三)残 照
4 御嶽山信仰
(一)御嶽山の祭り
(二)籠堂アルマヤ堂ありき
5 伊釜山
6 唐 沢
(一)北條家の屋敷
(二)信仰の中心地
(三)教育の中心地
(四)孝子桜考
(五)エドヒガン桜受難
(六)新道できる
7 中 嶋
(一)名主北條家
(二)兵法稽古道場
(三)丹後塚
(四)北條家家伝書
(五)石 屋
8 日吉山王
(一)山ノ峯の日吉山王
一、小社あり
二、石造物の奉納
(二)日吉神社となる
(三)日吉神社に拝殿ができる
9 堀之内
(一)神主屋敷
(二)北條松庵ゆかり地
(三)板碑あり
(四)魔除石あり
(五)渡部氏の移住
10 迎之内
11 弘蔵院
(一)弘蔵院の過去帳
(二)弘蔵院境内
(三)旧廟所跡
(四)移転した廟所
(五)黒石山
12 久保薬師堂
(一)瑠璃殿
(二)久保薬師堂の石造物
13 桑木沢
14 上足軽
(一)芝山さま
(二)日枝山王
(三)日枝神社の石造物
(四)福壽院跡
(五)熊野神社
(六)熊野台に運ばれた薬師堂
15 新 田
(一)結城街道
(二)市場星宮
(三)新 開
16 高 谷
(一)古戦場高谷
(二)高谷の里
(三)高谷から西田中へ
一、かうや川通り
二、戦後開拓の地
17 田中の薬師堂
(一)田中薬師堂の石造物
(二)田中の地
18 西稲荷の星宮
19 東稲荷
(一)稲荷大明神
(二)稲荷の薬師堂
(三)西善寺跡
20 内倉原
(一)村境白石口
(二)戊辰の役の見張り場
(三)内倉余話
一、硯 石
二、陸軍演習地
三、岩窟の無縫塔
21 赤岩山
22 鏡 沼
23 権現山
(一)権現塚
(二)権現山祭り
(三)権現山廟所
(四)祭祀の場