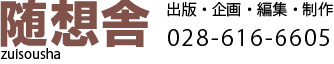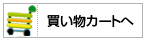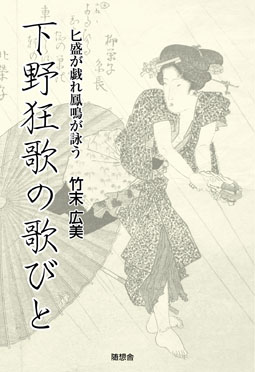
下野狂歌の歌びと
匕盛が戯れ鳳鳴が詠う
竹末 広美
下野発、狂歌の世界が広がる。
本書は、狂歌に親しみ、狂歌で結ばれた下野の歌びとに光をあてる。第一章で、通用亭・散木子らの狂歌紀行ともいうべき『四季の遊』を翻刻し、第二章では、下野の「連」の活動を資料に基づいて解説する。第三章では、下野の狂歌師をできるだけ採集し、狂名・略歴を作品とともに紹介する。最終章では、近世下野の歴史と人物を狂歌・落首でたどる。(「はじめに」より)
四六判/上製/376頁/定価3300円(本体3000円+税)
ISBN 978-4-88748-295-1
2014年8月28日 第1刷発行
著者プロフィール
竹末広美 (たけすえ ひろみ)
1953年、栃木県に生まれる。
学習院大学法学部卒業。現在、今市工業高校教諭。
『藤原町史』・『いまいち市史』・『鹿沼市史』の各編さん委員を務める。栃木県歴史文化研究会会員。
著書に『下野じまん─番付にみる近世文化事情─』『日光の司法─御仕置と公事宿─』『日光の狂歌─二荒風体を詠む』『下野の俳諧─風雅の人ここにあり』(随想舎)、論文に「日光宿の研究」(『歴史と文化』創刊号)などがある。
第1回ふるさととちぎ歴史文化研究奨励賞受賞。
目 次
第一章 『四季の遊』を詠む
第二章 下野の「連」の活動
1 概説
2 「連」の活動
第三章 下野の狂歌師
1 天雲仲道と足尾村の歌びと〈足尾〉
2 呉服堂織輔と足利連〈足利〉
3 壺枕亭三千成と今市宿の歌びと〈今市〉
4 糟粕園文車と氏家連〈氏家〉
5 下野庵宮住と宇都宮連〈宇都宮〉
6 玄仲那言匕盛と十返舎一九〈大田原〉
7 通蛙園章成と檀連〈大平〉
8 清藻園魚文と太平山〈太平山〉
9 浅鴬庵竹村と小山連〈小山〉
10 散木子安良と鹿沼連〈鹿沼〉
11 葦園正名と大芦連〈鹿沼〉
12 文の門梅良と下小倉村の歌びと〈上河内〉
13 上三川村と「下野歌枕」の歌びと〈上三川〉
14 常陸帯長と烏山芙蓉連〈烏山〉
15 喜連川町と『狂歌写玉袋』の歌びと〈喜連川〉
16 持雲斎喰鯛と黒羽連〈黒羽〉
17 六維園糸屑と佐野連〈佐野〉
18 桃林舎枕石と塩原の歌びと〈塩原〉
19 生得大酒と田沼連〈田沼〉
20 桜籬亭家住と馴垣連〈都賀〉
21 通用亭徳成と栃木連〈栃木〉
22 宝来亭島人と那須連〈那須〉
23 真名の門文照と馴垣連〈西方〉
24 鳳鳴閣と山水連〈日光〉
25 河野守弘と二宮連〈二宮〉
26 森琴亭真問と卍連〈野木〉
27 鼓腹亭実と烏山慈願寺歌合〈芳賀〉
28 大金重貞と「百観音巡礼記」〈馬頭〉
29 壺芳園顕雄と吉田村の歌びと〈南河内〉
30 遅日庵根向と助谷村の歌びと〈壬生〉
31 小宅文藻と真岡連〈真岡〉
32 真垣庵菊人と茂木連〈茂木〉
第四章 狂歌・落首に見る下野
天正一八年(一五九〇)、細川忠興が雄長老に狂歌を贈る
慶安四年(一六五一)、将軍家光が死去する
寛文一二年(一六七二)、浄瑠璃坂の敵討おこる
享保一〇年(一七二五)、大久保常春が烏山藩主となる
享保一三年(一七二八)、将軍吉宗が日光社参を挙行する
明和九年(一七七二)、日光社参が延期される
明和期、柳下泉が日光に参詣する
安永元年(一七七二)、輪王寺本坊が炎上する
安永五年(一七七六)、将軍家治が日光社参を挙行する
安永五年(一七七六)、四方赤良が日光へ随行する
天明三年(一七八三)、浅間山の大噴火
文化五年(一八〇八)、志賀理斎が日光へ参詣する
文化期、歌麿が「深川の雪」を描く
文政七年(一八二四)、水野忠成が日光へ参詣する
文政期、一橋家の家臣が宇都宮宿で消える
嘉永六年(一八五三)、ペリーが浦賀に来航する
文久三年(一八六三)、尊氏像が梟首される
元治元年(一八六四)、天狗騒動が起こる
慶応元年(一八六五)、宇都宮藩が棚倉国替えを命ぜられる
慶応三年(一八六七)、大関増裕が海軍奉行となる
慶応四年(一八六八)、下野北部の戦いが行われる